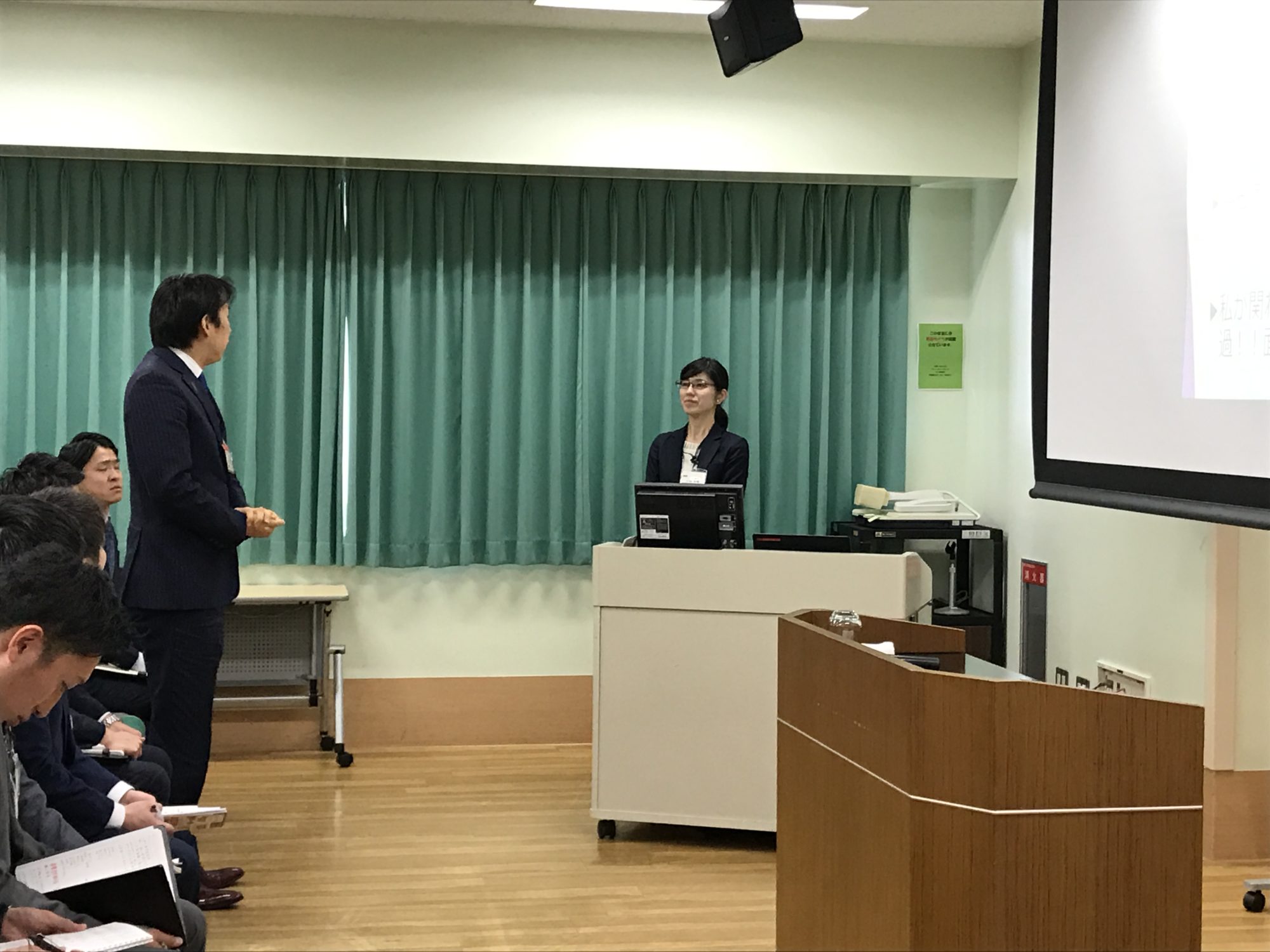7/7
ネクサス事業部の柳下です。
本日の室舘塾ユースについてお伝えします。
まず初参加の方が40名ほど、自己紹介をしました。
その時に、聞く側の姿勢についてお話をいただきました。
40人もの自己紹介を、自分に関係ないからと、ぼーっと聞くのはリーダーではない。リーダーは自分のための情報だけでなく、周りの方に共有したり話せるように情報を集めている。
という話がありました。
●何が当たり前の基準なのか
20代、30代の時に得た基準というのは、40代、50代になった時に戻れる軸になります。20代の今、何をどの基準でやるかが大切。それを教えるのが室舘塾ユースです。
室舘代表は茶道を8年間続ける中で、少しでも早く師範になるために、お稽古を皆勤で参加されました。
さらに、室舘代表が意識したのが「見取り稽古」。技術や手順はもちろん、特にお手本となる方の空気感、お点前を感じることが大切と思い、自分がお点前をする以外の時間も見て学んでいました。
ボーッと座っているのか、見取り稽古をしているのかでは成長に差が出ます。
●映画を観るポイント
幹部候補生やマネージャーに対して課題映画を与え、感想を共有する場がある。
ただ映画を観るのではなく、例えば監督がキャスティングした俳優の顔を見ることを意識すると良い。
正義のヒーロー役の顔、悪役の顔、裏切り者の顔など、目利きの能力がつき、人を見抜く力が養える。
●国歌を歌う意義
室舘塾ユースでは冒頭、国歌を歌います。
その理由として、自国の国旗、国歌に敬意を表せない人は、他国の国旗、国歌にも敬意を表せない、ということを体感するためです。
日本が嫌い、故郷が嫌い、自分・家族・会社を嫌いと思っている人はどこか影があり信用ができません。
日本では国歌を歌わない人が多くなりました。しかし、アメリカでは幼稚園から国歌を歌っていてみんな大好きだそうです。
それはアメリカが移民国家であり、日本は単一民族国家なので危機感が薄いという違いも一つ原因となっています。
●日本のここ100年の流れ
1904~5年には日露戦争がありました。
日露戦争から大東亜戦争まで、日本は非常に強い国でした。
1941年12月8日から開戦した大東亜戦争。
日本、ドイツ、イタリアは連合国と敵対関係にあったため、いまの国際連合(UN-United Nation)の常任理事国には入っていない。
3年8ヶ月にも及んだ大東亜戦争でポイントとなったのが硫黄島の戦い。硫黄島は「不沈空母」とも呼ばれ、日本本土への空爆を狙うアメリカにとってなんとしても制圧したい領土であった。
硫黄島には、食料も水もなく、アメリカは3、4日で終わると思っていた。しかし日本軍は、日本本土の家族を守るために戦いを長引かせ、栗林忠道が玉砕を禁じて最後の一人まで戦った結果、なんと37日も戦いを長引かせました。
また、神風特攻隊はじめ、自分の意思で特攻していく日本兵が4000人もいて、PTSDになるアメリカ兵も出ました。
アメリカ軍はもう日本とは戦いたくないと誓い、GHQは二度と日本が立ち上がらないように、占領政策として弱体化、白痴化を狙い、様々な政策をしました。
東京裁判、財閥解体、WGIP、国民と軍人の分断化、図書没収令、公職追放令などです。
●国護り
GHQの政策のうち、キャリアコンサルティングが注目したのが公職追放令です。キャリアコンサルティングは「逆公職追放令」として、良いリーダーを育成することをおこなっていきます。
一人ひとりの若者が「食べたい、寝たい、楽しみたい」と言った我欲を追求することも良いかもしれませんが「一度きりの人生、それだけではイヤだ。何か公のため、人のためになることがしたい」という若者もいます。
そういった若者が集まるのが室舘塾ユースです。
普通に会社に勤務して人生が進み、30代、40代になると「何だろう自分の人生」と思う人もいるそうです(ミッシングリンクとも言うそうです)。
本来、ライスワーク(生活するための仕事)とライフワーク(人生で成し遂げたい仕事)が一致してこそ、人生は最大限に豊かになっていきます。
「実力のある人が要職に就き、誠実に働けば国はすぐに良くなる」
室舘代表が掲げる「国護り」に共感する若者を増やし、一回しかない人生を最大限に活かしていく若者を輩出していくことが大切です。
以上、7月の室舘塾ユースはとても情報量が多く、気づきと学びがとても多かったです。
日本の歴史や、人生の捉え方など20代の根っことなるお話が詰まっていて、レベルアップできました。
ありがとうございました。